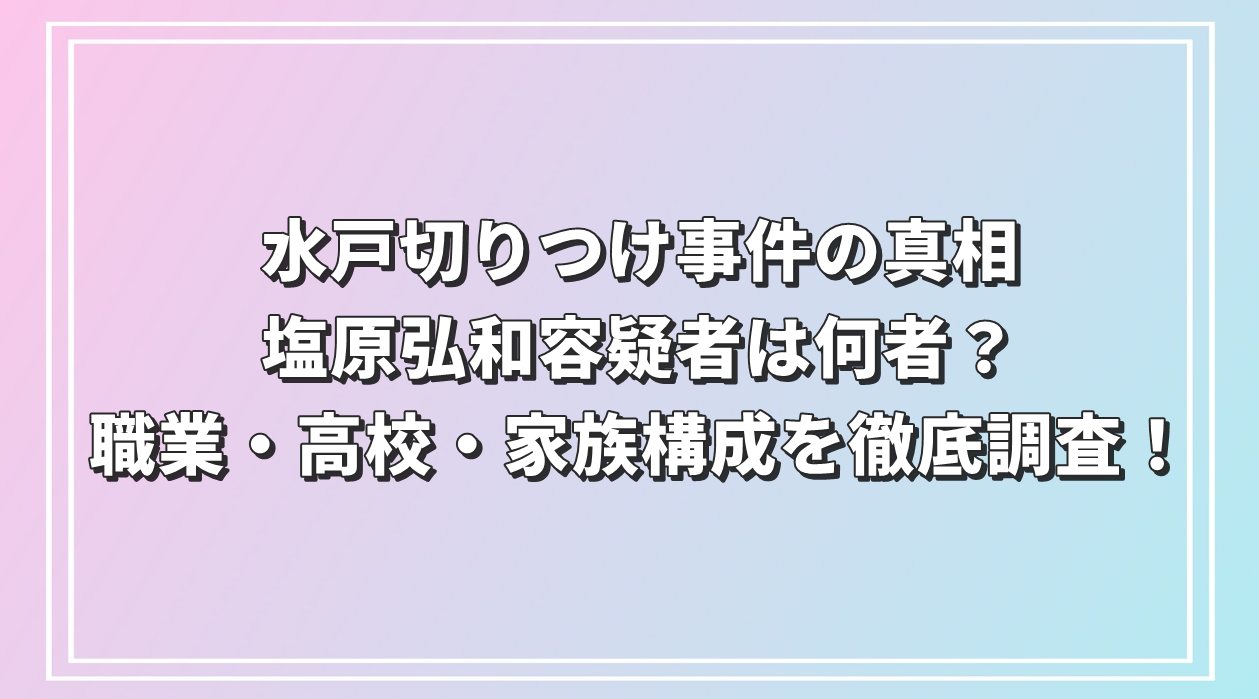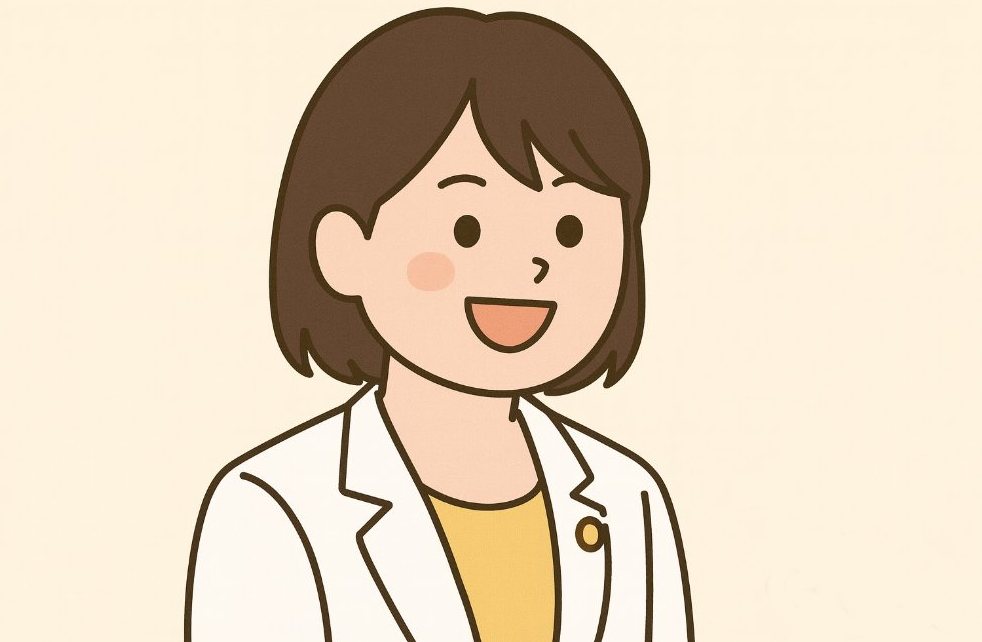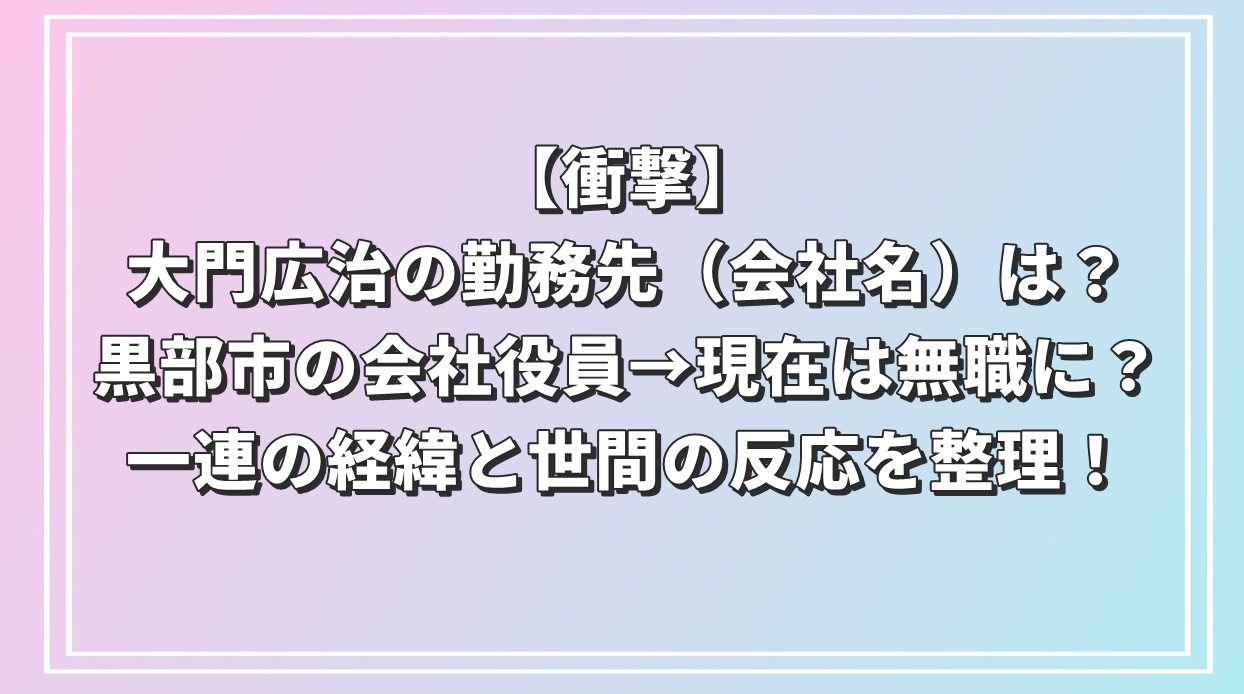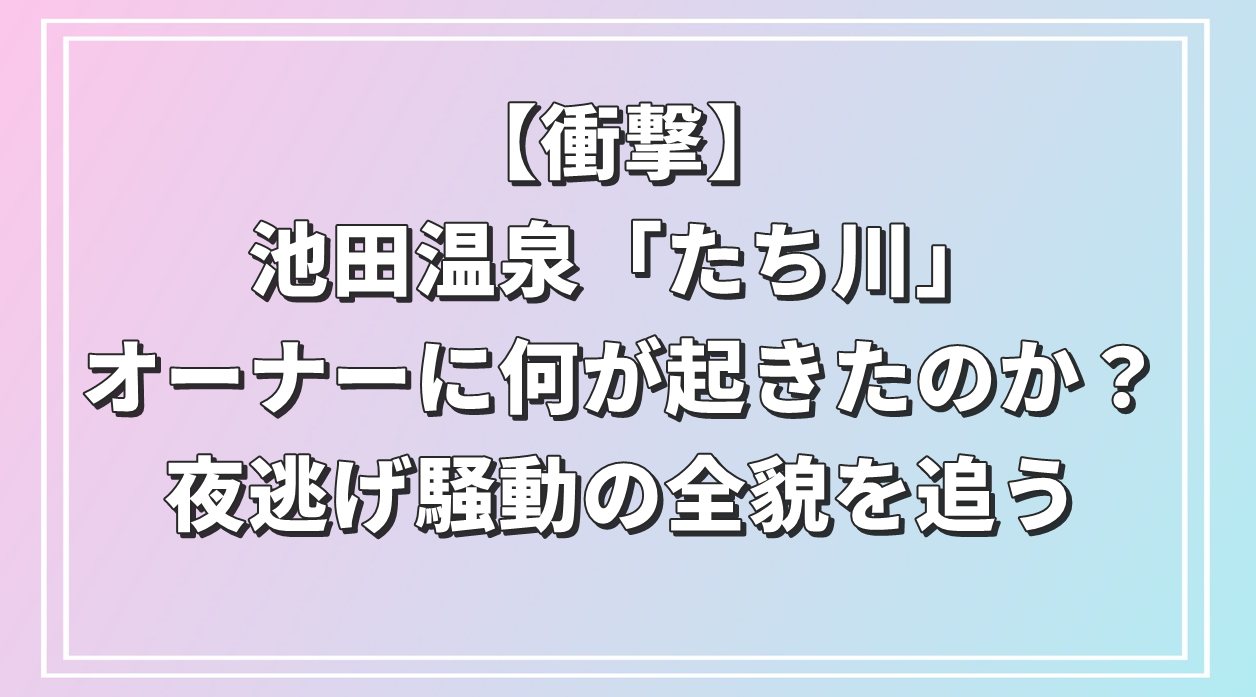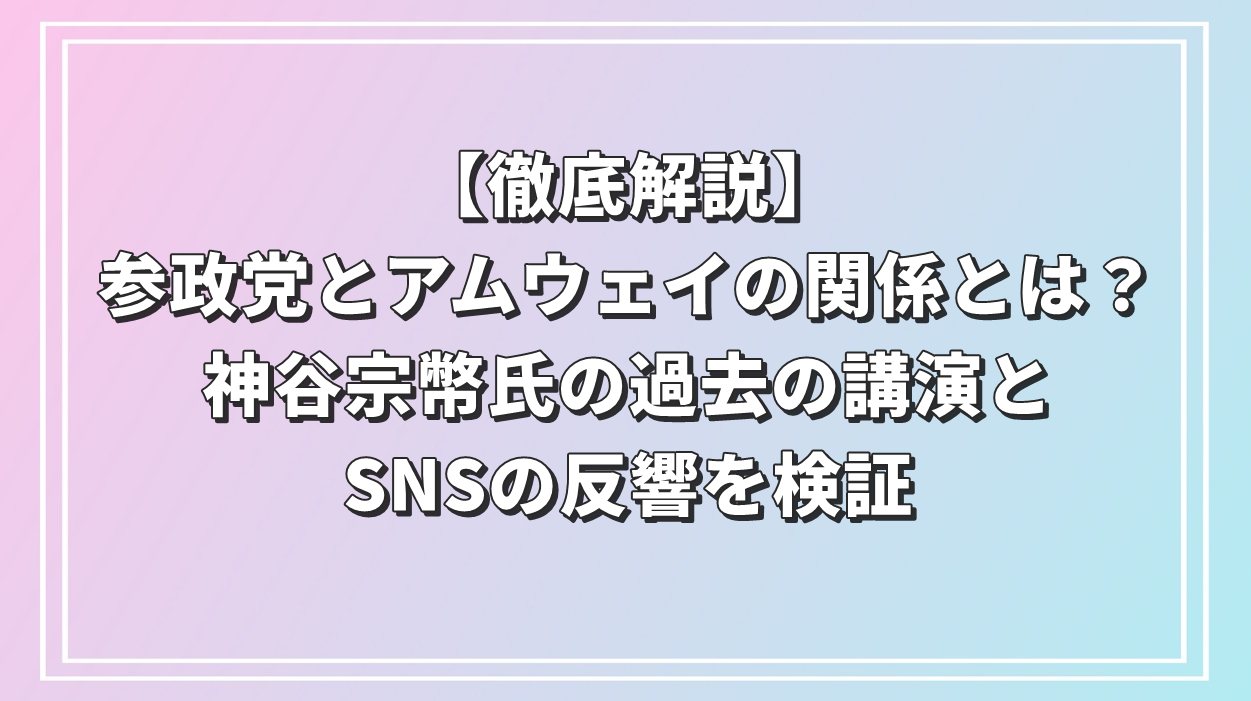自民党本部での取材待機中に飛び出した「支持率下げてやる」という言葉。
ネットで大きな波紋を呼んだこの発言の主は、時事通信の大ベテランの中年男性カメラマン であることが会社の調査で特定されました。
「一体誰なの?実名や名前は?」とSNSでは“犯人探し”が過熱しましたが、現時点で公表されたのは 時事通信の男性カメラマン という肩書きだけ。
本人は厳重注意を受け、時事通信も公式に謝罪しました。
報道の現場で「中立性」が疑われる発言が出てしまった今回の騒動。
ネットでは「処分が甘すぎる」「オールドメディアの体質だ」と批判が相次いでいます。
この記事では、
- 問題の発言がいつどこで起きたのか
- 発言者がどう特定されたのか
- 時事通信社の謝罪と処分内容
- ネットや永田町での反応
- 記者クラブ文化や報道機関の体質問題
などを詳しく整理し、「今回の騒動が何を意味するのか」をわかりやすく解説していきます。
発言があった経緯|なぜ「支持率下げてやる」が問題になったのか?
いつ、どこで発言が飛び出したのか?
今回の騒動が起きたのは、2025年10月7日の午後です。
場所は東京・永田町にある自民党本部。
この日、高市早苗総裁と公明党との連立協議が行われ、その後の取材対応を待つため、多くの記者やカメラマンが4階フロアに集まっていました。
高市総裁の登場を待つ間、報道陣の間には緊張と退屈が入り混じった独特の空気が流れていたといいます。
そんな中で問題の言葉がマイクに拾われました。
発言の内容とは?
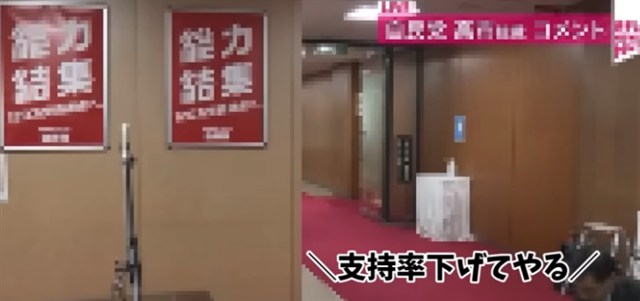
ネットの生中継映像にしっかり収録されていたのは次の言葉です。
- 「支持率下げてやる」
- 「支持率が下がるような写真しか出さねえぞ」
いずれも報道機関の人間が口にしたとは思えない、きわめて偏ったニュアンスのある発言です。
この音声が流れるや否や、SNSでは「誰が言ったんだ?」と大騒ぎになりました。
政治家本人を前にした場での不用意な発言が、即座に世論の炎上を招いた格好です。
SNSでの拡散と波紋
X(旧Twitter)では、この発言を切り取った動画が瞬く間に拡散されました。
「マスコミがこんなことを言っているのか」
「報道の中立性はどうなっている?」
そんな批判が一気に噴出し、「#支持率下げてやる」が関連ワードとしてトレンド入りする事態に。
当日の夜から翌日にかけて、ニュースサイトやまとめブログも次々に取り上げ、炎上はさらに拡大していきました。
 管理人
管理人この件について私が思うのは、たとえ雑談でも全国に流れる可能性がある時代に軽口は命取りだな、ということです。
もう「オフレコ」なんて通用しない世の中ですよね。
※参考サイト:「支持率下げてやる」発言は時事通信社のカメラマン 厳重 …
発言者は誰?特定されたのは時事通信の大ベテランカメラマン
発言者が特定された経緯
「支持率下げてやる」という音声がSNSで大炎上した直後、ネット上では“犯人探し”が始まりました。
しかし、時事通信社は9日に公式発表を行い、発言者が 自社の映像センター写真部に所属する男性カメラマン であると明らかにしました。
この人物は取材現場で長く活動している 大ベテランの中年男性カメラマン。
雑談のつもりで軽口を叩いたとされますが、その一言がライブ配信にしっかり残り、拡散したことで世間の信頼を大きく揺るがす結果となりました。
実名や名前は公開されていない
読者が一番気になるのは「実名や名前は?」という部分でしょう。
しかし、時事通信社は実名を公表していません。
公表されたのは以下の情報だけです。
- 所属:映像センター写真部
- 性別:男性
- 年齢層:中年(ベテランと報じられている)
そのため「誰なのか」「顔や名前は?」といった疑問がSNSで飛び交う一方、プライバシー保護の観点から実名は非公開のままです。
時事通信の立場と説明
会社側は、本人が発言したのは事実と認めつつも、他に拡散している一部の音声は別の人物のものであると説明しました。
つまり、問題となった発言のすべてをこのカメラマンが行ったわけではない、という立場です。
それでも核心的な「支持率下げてやる」「支持率が下がるような写真しか出さねえぞ」という発言については、この男性カメラマンのものだと特定されました。



実名非公開なのは当然かもしれませんが「大ベテラン」と報じられることで余計に信頼失墜が大きいな、という点です。
若手の失言ならまだしも、長年取材してきた人の口から出た言葉だけに重みがありますね。
時事通信社の対応と公式謝罪|処分は「厳重注意」のみ


会社が発表した内容
炎上から2日後の10月9日、時事通信社は公式サイトとX(旧Twitter)で声明を発表しました。
そこでは、発言が 映像センター写真部の男性カメラマンによるもの であると認めたうえで、本人を「厳重注意」処分にしたと公表しました。
声明には以下の内容が記載されています。
- 発言は取材待機中の雑談だった
- 報道の公正性・中立性に疑念を抱かせた
- 男性カメラマンを厳重注意処分とした
- 関係者に不快感を与えたことを謝罪する
幹部のコメント
藤野清光(ふじの・きよみつ)取締役編集局長は、次のようにコメントしました。
また、斎藤大(さいとう・まさる)社長室長も声明を出し、
と述べました。
「厳重注意」に批判殺到
一方で、ネット世論の反応は冷ややかです。
- 「厳重注意なんて実質お咎めなし」
- 「マスコミは政治家や企業の不祥事には厳しいのに、自分たちには甘い」
- 「せめて配置転換や謹慎が必要では?」
など、処分が軽すぎるという意見が多数を占めました。
「公平・中立」を掲げる報道機関の人間が政治家に対して「支持率下げてやる」と言った以上、厳しい対応が求められて当然だという空気感が広がっています。



「厳重注意」で済ませたのは弱すぎる対応だなということです。
マスコミが他人に厳しい論評をする以上、自分たちにも同じ基準を課さないと信用は戻らないですよね。
参考サイト:本社カメラマンを厳重注意 「支持 …
ネットの反応と世間の声|「厳重注意は甘すぎる」の大合唱
SNSでの炎上と拡散
「支持率下げてやる」という音声が生中継に流れた直後から、X(旧Twitter)を中心に猛烈な勢いで拡散しました。
わずか数時間で数十万件の投稿やコメントが集まり、大きな社会問題として注目されることになりました。
代表的な批判の声
SNSやコメント欄には厳しい意見が相次ぎました。
- 「厳重注意で済むのは甘すぎる。普通の会社なら懲戒もの」
- 「マスコミは政治家や企業に厳しいのに、自分たちには甘すぎる」
- 「ベテランカメラマンがこれじゃ報道の信頼なんて保てない」
- 「偏向報道の体質が透けて見える。これで中立と言えるのか?」
多くの人が「処分の軽さ」や「マスコミ全体の体質」に強い疑問を投げかけていました。
一部にある擁護の声
一方で、「取材現場は待ち時間が長く、軽口も飛び交うもの」という擁護の声も一部では見られました。
ただし、その声も少数派で、圧倒的多数は「報道の中立性を揺るがす発言を軽く流すべきではない」という批判的な意見に傾いています。
永田町でも波紋
政治の中心地・永田町でも今回の件は話題となりました。
高市早苗総裁をはじめ、与党関係者からは「報道機関として不適切」との不快感が示されており、マスコミと政治の関係性に影響を与えかねない事態となっています。



ネットの声は決して“言い過ぎ”ではなく、むしろ当然の反応だということです。
報道の信頼が一度失われたら、取り戻すのは本当に難しいですよね。
永田町取材現場の実情|軽口と緊張が入り混じる独特の空気
待機時間に漂う“ゆるみ”
政治の中心である永田町、自民党本部の取材現場は常に多くの記者やカメラマンでごった返しています。
大臣や総裁が登場するのを数時間待つことも珍しくなく、その待機時間に記者やカメラマン同士で雑談が始まることは日常的です。
政治部のベテラン記者によれば「もっとひどい冗談や皮肉が飛び交うこともある」といい、今回の発言もその延長線上にあったとされています。
ただし今回は、偶然にもそのやり取りがライブ配信に乗ってしまったことで“冗談”では済まされなくなったのです。
クローズドな環境が生む体質
永田町の取材現場は、いわゆる「記者クラブ」に所属する記者やカメラマンが集まる、ある意味で閉ざされた空間です。
この環境では次のような特徴があります。
- 同じ政治家を日々追いかけるため、記者同士に“仲間意識”が生まれやすい
- 待機中に愚痴や軽口を言い合うのが常態化している
- 昔からの慣習が残りやすく、外部の目が届きにくい
つまり、外から見ると異様に感じられる「気の緩み」が内輪のノリとして許されてきたのです。
“昭和的オジサン文化”の残骸
特に指摘されているのが、ベテラン世代のカメラマンや記者の存在です。
- 若手に比べて発言が荒い
- 冗談や皮肉の度が過ぎる
- 「昔はこれくらい普通だった」という感覚が抜けていない
こうした“昭和的オジサン文化”が、現代のSNS時代にまったくそぐわないことは言うまでもありません。
現場の空気としては「いつものこと」でも、世間に広まれば炎上必至なのです。



記者クラブの閉鎖性がこうした問題を温存してきたんだろうなということです。
やっぱりオープンな監視の目がなければ、古い体質は変わらないんだなと強く感じました。
今回の騒動が意味すること|報道の信頼とマスコミ不信の加速
雑談でも許されない時代へ
今回の「支持率下げてやる」発言は、当人にとっては取材現場の雑談にすぎなかったのかもしれません。
しかしSNSとライブ配信が当たり前になった今、現場の軽口ですら全国に届き、瞬時に炎上する時代です。
「誰も聞いていないだろう」という意識はもう通用せず、記者やカメラマンの一言一言が世論に影響を与える可能性を持っています。
「現場に権限はない」という言い訳
時事通信社をはじめ一部の記者は「現場のカメラマンに論調を左右する権限はない」と説明しました。
ですが、写真や映像が世論形成に与える影響は絶大です。
たとえば政治家の一瞬の表情を切り取った写真が、ネガティブなイメージを広めてしまうこともあります。
つまり「権限がない」という言い訳は、国民の納得を得られないどころか、逆にマスコミ不信を深めてしまう結果となっています。
オールドメディアの構造的な病理
この問題は、個人の失言にとどまらず、業界全体の体質を映し出しています。
- 記者クラブという閉鎖的な空間
- ベテラン中心の“昭和的”体質
- 組織ぐるみでの自浄作用の欠如
- 世論を軽視した内輪ノリの文化
こうした要素が重なり、「オールドメディア」と揶揄される存在感をさらに強めてしまいました。
今後に求められるもの
今回の騒動が示すのは、報道機関に求められる“透明性と倫理意識”の高さです。
ネット社会では、どんなに小さな失言でも一瞬で拡散され、取り返しのつかない事態につながります。
報道の現場にいるすべての人が、「国民にどう受け止められるか」という視点を常に持つ必要があるのです。



「マスコミ離れ」がますます進むきっかけになりそうだなということです。
国民の信頼を取り戻すには、もう小手先の謝罪じゃ足りないんだと思います。
よくある質問(FAQ)
Q1. 「支持率下げてやる」と言ったカメラマンの実名はわかっているの?
現時点で 実名や名前は公表されていません。
特定されたのは「時事通信社の映像センター写真部に所属する大ベテランの中年男性カメラマン」という情報のみです。
SNSでは“犯人探し”が過熱しましたが、会社はプライバシー保護の観点から名前を公開していません。
Q2. 本当にその人だけが発言したの?
問題の「支持率下げてやる」「支持率が下がるような写真しか出さねえぞ」という発言は、この男性カメラマンによるものと特定されています。
ただし、それ以外にネットで拡散した発言の一部は別の人物のものだと、時事通信社は説明しています。
Q3. どんな処分を受けたの?
会社はこの男性カメラマンを 「厳重注意」 という内部処分にしました。
配置転換や懲戒といった重い処分ではなく、形式的なお咎めにとどまっています。
そのため「甘すぎる」という批判が多く集まっているのが実情です。
Q4. この件で時事通信社はどう対応したの?
会社は公式サイトとX(旧Twitter)で謝罪文を掲載し、幹部もコメントを発表しました。
「報道の中立性に疑念を抱かせた」として謝罪したものの、世間からは「言い訳に聞こえる」と厳しい意見も出ています。
Q5. 今後同じようなことは起きないの?
再発防止策として「社員教育や指導を徹底する」と時事通信社は表明しました。
しかし、記者クラブ文化や現場の“昭和的な空気”が根強く残る限り、同じ問題が再び起きるのではないかという懸念の声は少なくありません。
Q6. 共犯者はいるの?誰?
今回の発言以外にもSNSでは別の音声が拡散しており、時事通信社は「それは別人によるもの」と説明しています。
つまり、“主犯”とされるカメラマン以外にも現場で不適切な発言をした人物がいる可能性は否定されていません。
ネットや一部動画配信者の間では「まだ他社の記者やカメラマンが関与しているのでは?」との指摘もあり、今後の調査次第で“共犯”が浮かび上がる可能性があります。
まとめ|“支持率下げてやる”発言が残した教訓とは
今回の騒動を整理すると、次のようになります。
- 発言があったのは 10月7日午後、自民党本部の取材待機中。
- 問題の言葉は「支持率下げてやる」「支持率が下がるような写真しか出さねえぞ」。
- 発言者は 時事通信社・映像センター写真部所属の大ベテランの中年男性カメラマン。
- 実名や名前は公表されず、処分は「厳重注意」のみにとどまった。
- 時事通信社は公式に謝罪したが、ネットでは「甘すぎる」と批判が殺到。
- 記者クラブ文化やオールドメディアの閉鎖性が改めて問題視された。
今回の件は、一人のカメラマンの不用意な発言に見えて、その裏には「報道の中立性への不信感」という大きな問題が潜んでいます。
SNS時代では、現場の軽口であっても即座に全国に届き、世論を揺るがす事態になり得ます。
だからこそ報道関係者には、より高い倫理観と緊張感が求められるのです。



やっぱり報道に関わる人は「見られている意識」を常に持つべきだということです。
一瞬の油断が信頼を壊す時代だからこそ、軽口こそ一番危ないんですよね。